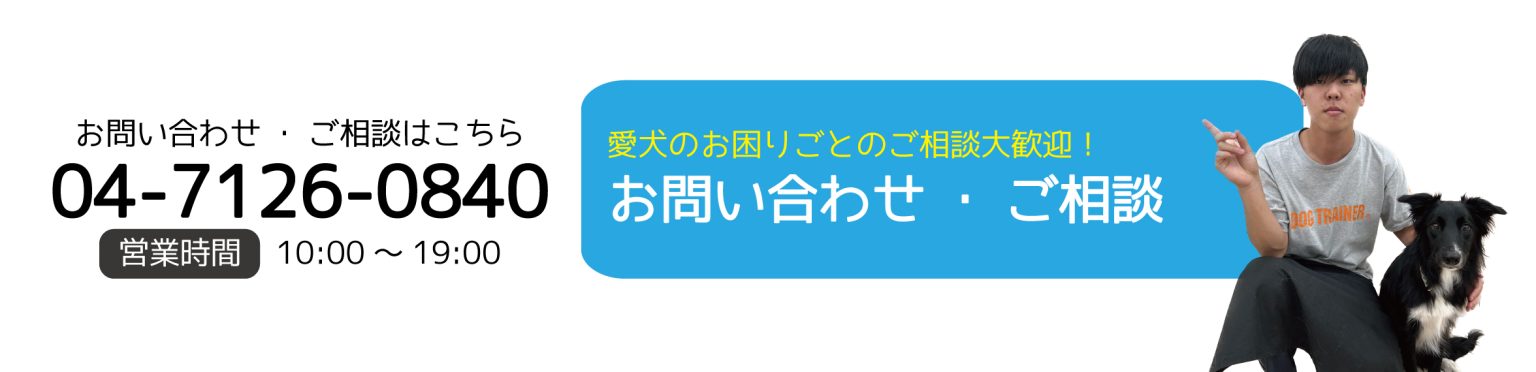「他の犬が怖くてお友達ができない」
「人が触ろうとすると、逃げたり、唸ったり吠えてしまう」
「お外が怖くて尻尾が下がっていて楽しくお散歩できない」
などなど、『うちの子、もしかして怖がりなのかな…』と感じたこ
愛犬に楽しく過ごして欲しいのに怖いものがあるとストレスになっ
また、「うちの子が怖くて吠えることで、相手の方にも嫌な思いを
「無理にでも触れ合わせて慣らせたほうがいいのかな?」
そう悩む飼い主さんは本当にたくさんいらっしゃいます。
でも、どうかひとつだけ、忘れないでいてください。
あなたの子が「怖がり」なのは、性格が悪いからでも、しつけがで
「怖がり」は悪いことじゃない
怖がりの子の行動の奥には、「怖い」「どうしたらいいかわからない」
そんな小さなSOSのサインが、隠れているだけなんです。
決して、わがままや性格のせいではありません。
犬が怖がりになってしまう背景は、犬によってさまざまです。
•幼少期に十分な社会化経験がない
•過去に怖い思いをした
•もともと繊細な性格
一見「問題行動」に見える反応も、すべては「自分の身を守るため
まずはその怖がる気持ちに、そっと寄り添ってあげることが大切で
怖がりさんにもいろんなタイプがいる
実は、怖がっている子たちにも、いろんなタイプがいます。
•逃げる、隠れるように避ける子
•吠えたり唸ったりして、自分を守ろうとする子
•一見平気そうに見えて、実はじっと固まって我慢している子
どの子もみんな、不安や恐怖を感じています。
その「感じ方」や「表現の仕方」が違うだけなのです。
だからこそ、一律のやり方ではなく、その子に合った方法で少しず
そして、【犬の気持ちに寄り添うこと】は、私たち犬のがっこうエ
ただ方法を押しつけるのではなく、
その子が今、どんな気持ちでいるのかを、できる限り丁寧に見てい
表情やしぐさ、動きや呼吸の変化。
「今はまだ緊張しているな」「この子は無理をしていないかな」
そんなサインを見逃さず、犬の気持ちを置き去りにしないことが、
そのうえで、「少しずつ慣れていく」ためのステップを以下のよう
「基礎訓練」で心の土台をつくる

まずは「おすわり」「まて」「ついて」などの基本的な指示ができ
これは単なる「芸」ではなく、人の声を聞いて落ち着いて動ける心
心が不安定なまま無理に慣らそうとしても、かえって怖さが強くな
まずは「安心して、人の声に耳を傾けられる状態」を目指しましょ
他の犬に慣れていく練習

犬たちは、「この前こうだったから、次もそうだろう」と経験から
もし「他の犬=怖い」と感じていたら、近づきたがらないのは当然
だからこそ、「大丈夫だった」「怖くなかった」
そんな経験を少しずつ積み重ねていくことが、気持ちの変化につな
①距離をとってすれ違う練習から
落ち着いた犬と、5mほど離れた距離ですれ違うところからスター
最初は、相手の存在を気にしないくらいの距離感でOK。
徐々に距離を縮めていき、もし吠えたり緊張が高まったら、すぐに
「怖くなかったね」を積み重ねていくことがポイントです。
②ノーリードで自然な関わりを
お互いが落ち着いてきたら、広くて安全な場所で、ノーリード(リ
•相手の犬に攻撃性がないことをしっかり確認
•犬が自分から近づくのを待つ
•少しの進歩でもしっかり褒めてあげる
•飼い主さんが近くにいすぎると甘えが出ることも。状況によって
※注意※
ドッグランは刺激が強すぎるため、怖がりな子には逆効果になるこ
また、パピー限定の幼稚園では、成犬の社会化に対応できない場合
だからこそ、私たちは年齢に関係なく、その子のペースで犬同士の
人に慣れていく練習

人に対して怖さを感じる子には、「この人は怖くないんだよ」と伝
•しゃがんで、犬を見ずに静かに待ってもらう
•犬は抱っこせず、地面に下ろして(逃げられる状態を作る)
•犬が興味を持ったら、手の甲のニオイを嗅がせる(指は出さない
•嗅げたらしっかり褒める
•可能なら、その人からおやつをもらったり、投げてもらったりす
このように少しずつ関わっていくことで、「人=怖くない」「人=
また、練習を通して、「この子はどんな接し方なら安心できるか」
もし、すでに強く反応してしまう場面がある場合も、決してあきら
無理せず、その子に合ったサポートを一緒に探していきましょう。

焦らなくて大丈夫です。
少しずつでいいんです。
怖がりな子にとって「慣れる」ということは、とても大きなチャレ
でも、その子なりのペースで、ひとつずつ乗り越えていくことで、
私たちは、犬のペースを大切にしながらその子の「がんばった一歩」を一緒に喜び、応援し、支える存在で
【無理に慣らす】のではなく、【安心できる方法で、少しずつ進む
「この子に合ったやり方で寄り添いたい」
そう思ったときが、一歩を踏み出すタイミングです。
私たちと一緒に、その子らしいペースで、楽しい世界を少しずつ広
あなたと愛犬のペースに寄り添う、そんなお手伝いができたら嬉し
「まずは話を聞いてみたい」そんな気持ちだけでも大丈夫です。
まずは、無料カウンセリングから始めて下さい。